愛犬の肥満に悩んではいませんか?
獣医さんに指摘されてしまったけれど、どうやって減量するのが適切なのかよく分からない。そもそも、肥満ってそんなに気にしなければならいの?
何だか太った気がするけど、特に元気そうだし大丈夫と思っていませんか?
実は、犬の肥満は大病をもたらす大きなきっかけとなり、そのまま放っておいたら大変な事になってしまいます。
毎日見ていると、なかなか気が付きにくいものですが、犬の体重管理も飼い主さんの大切な役割です。
今回は、犬の肥満度のチェックから健康的なダイエット方法までご紹介します。
ダイエットの目標を決める
下記に犬の肥満度のレベルが分かります。
目標となる体型はBCS3の状態なので 、体重はBCS4なら10~20%の減量、BCS5なら20~40%の減量を目標とするといいでしょう。
長期的な計画を立てて、中間目標と立ててダイエットを行うと目標を達成しやすくなります。
犬に負担をかけてしまうため、決して短期間の減量はやめましょう。

愛犬の肥満度をチェック!
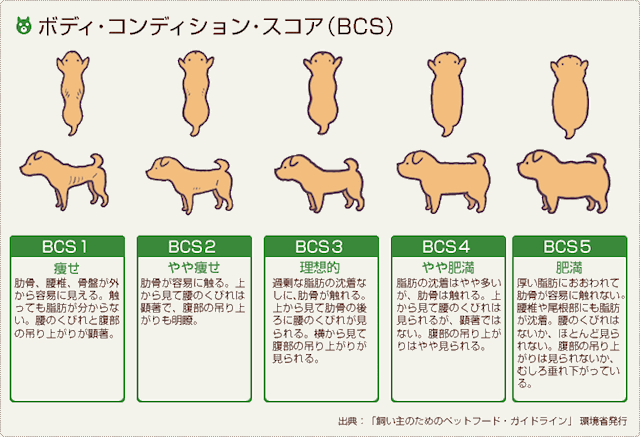
画像引用元:http://www.petline.co.jp
どの程度太ってしまっているのか、ダイエットが必要なのか確認しましょう。ペット用の体脂肪計もありますが、簡単に自宅でできるBCS(Body Condition Score)でチェックしてみましょう。
犬種や大きさによって標準値は異なりますが、確認するポイントは腰と肋骨周りです。BCS3を目標にして体重管理をしていきましょう。
BCS1 痩せすぎ
肋骨、腰骨、背骨が触らなくても見て分かる。横から見ると、お腹がとてもつり上がっていて、触っても脂肪に触れない。
BCS2 痩せ気味
肋骨に簡単に触れる。脂肪に触れる事は出来るが、上から見ると砂時計の様な形になっている。
BCS3 標準体型
適度な皮下脂肪の下の肋骨に触れる事が出来る。腰にはくびれがある。
BCS4 肥満気味
皮下脂肪が多く、肋骨に触れる事は出来るが難しい。上から見ると腰のくびれがやや見られる。
BCS5 太り過ぎ
厚い脂肪に覆われていて、肋骨に触れない。くびれが見られず、箱や樽の様な形をしている。

肥満になるとどうなる?
人と同じように犬も肥満になると様々な病気になります。特に関節や筋肉、心臓、呼吸器系の病気にかかりやすくなります。体重を支えきれずに骨が歪み、関節にも支障をきたして運動が困難になります。
また、心臓は全身に血液を送るために余計に働かなければならない事が大きな負担となり肥大化します。そして、呼吸数も増えるので呼吸器の負担も大きくなるのです。
肥満は食べ過ぎが原因の場合が多く、その場合は糖尿病などの内臓疾患のリスクも高まります。
フードを低カロリーなものにする
食事量自体を減らしてしまうと、ストレスがたまってイライラしたり、自傷行為をしてしまうわんちゃんもいます。
なるべく食事量は変えずに、フードのカロリーを抑えるやり方が効果的ですが、カロリーは抑えても栄養はきちんと取らなければなりません。
市販のドッグフードでも、ダイエット用の低カロリーなものはあります。
飼い主さんの時間が許されるなら手作りのフードもオススメです。
温野菜を沢山使ったり、新鮮なものから生きた酵素などを取り込む事ができます。

フードの与え方を見直す
肥満のわんちゃんに多いのが、一度に食べ過ぎてしまっているパターンです。
早食いをしてしまうと消化にも悪く、満腹中枢が刺激される前に食べ過ぎてしまいます。
1日のトータル量はそのままに、回数を分けたりコングなどを使用してゆっくりとフードを食べる工夫をするといいでしょう。
運動量を増やす
ダイエットに運動は必要不可欠ですが、あまりハードな運動は犬の身体の負担となってしまい、関節や筋肉を返って痛めてしまう恐れがあります。

普段のお散歩の途中でボール遊びをしたり、少し散歩コースを長く変えてみるなどの軽い運動から始めましょう。犬は飼い主さんとコミュニケーションをとりながら遊ぶと、楽しくカロリーを消費する事が出来ます。
運動嫌いなわんちゃんも、なるべく外に連れ出して気分転換をしてあげると運動をしてくれるかも知れません。散歩コースは階段や坂道、河原の土手などを歩くと運動量を増やすことが出来ますよ。
まとめ
人間同様、犬も肥満のまま放っておくと大変な事になります。
生活習慣病や糖尿病など、様々な病気のリスクが高くなり、寿命は平均体重の犬と比べると15%も短くなってしまいます。
犬の肥満は飼い主さんの責任なので、きちんと健康管理をしてあげるのは、大切な家族である愛犬の健康的な生活のために必要なことです。
少し太ったかなと感じたら、食事内容や運動量で調整し、大切なポイントを抑えて、無理せずにワンちゃんにあったダイエットを行いましょう。














